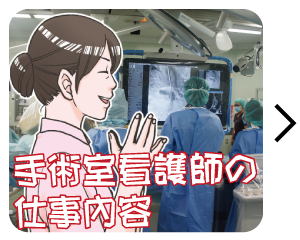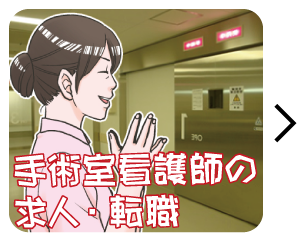当サイトはアフィリエイト広告を掲載しています
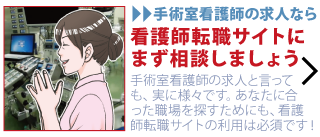
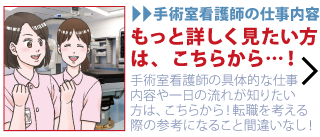
手術室看護師の立ちっぱなしによるトラブルは脚だけではありません
仕事で立ちっぱなしの業務は、手術室看護師だけではありません。例えば、衣料品などの販売員や飲食店の店員、エレベーターの乗務員など様々な職種が立ちっぱなしで業務をしています。
「立ちっぱなし」のトラブルはどれも同じ様に思いがちです。しかし、実は、仕事環境によって立ちっぱなしから生じるトラブルは、違ってきます。
手術室看護師の立ちっぱなしによるトラブルをご紹介します。
目次 [目次を隠す]
立ちっぱなしによる脚のトラブル
一般的に「立ちっぱなし」によるトラブルは、「脚」という方も多いかと思います。
長時間立っていることにより、下腿に血液が停滞することでうっ血を起こします。うっ血を起こすことで、むくみが生じたりだるさを感じるようになります。
脚のトラブルのケア
浮腫みやだるさのケアは、下腿のうっ血を緩和することがポイントになります。
下腿のうっ血を緩和するには、市販の弾性ストッキングを着用する方法があります。その他にも脚のマッサージやツボ押しなども有効です。
脚のトラブルを予防する
立ちっぱなしによる脚のトラブルを予防する方法は、前述した市販の弾性ストッキングの着用が有効と言われています。
バランスを崩した状態での立ちっぱなしは、下腿のうっ血を起こしやすくなります。だから、疲れにくい立ち方を取り入れることで脚のトラブルを予防できると言われています。
外回りの手術室看護師の立ちっぱなし
外回りの手術室看護師の業務は、医療施設によって異なります。そのため、患者の入室から退室するまでの立ちっぱなしについてご紹介します。
外回りの手術室看護師は患者の入室から退室まで立ちっぱなしです。しかし、外回りの手術室看護師は、直接介助の手術室看護師とは違って「動いています」。
静止状態の立ちっぱなし
外回りの手術室看護師が静止している立ちっぱなしは、あまり多くありません。外回りの手術室看護師が静止しているときは、患者の申し送りや術中の看護記録を記載している時などです。
脳外科手術や眼科の手術のようにマイクロを使用する術式では、外回りの手術室看護師がバタバタ動くと医師が手術に集中できないため、必要以上に動くことはしません。この様な術式では、外回りの手術室看護師は、術中は静止した立ちっぱなしが多くなります。
立ちっぱなしによるトラブルの回避
外回りの手術室看護師は、直接介助の手術室看護師に比べて脚のトラブルが生じる頻度は少ないです。
前述しましたが、脚のトラブルは、下肢の血流が停滞することで生じます。下腿の血流の停滞は、下肢の筋肉の収縮が低下することによって発症しやすくなります。
外回りの手術室看護師は、術中に無影灯の調節で踏み台を登ったり下りたりします。また、尿量の確認やガーゼカウントなどでしゃがむことがあります。この「動く」動作が多いことによって外回りの手術室看護師の下腿の血流の停滞は、直接介助の手術室看護師と比べて比較的少ない傾向にあります。
とは言うものの、外回りの手術室看護師が「動く」動作が多いといっても業務は、立っていることが長いため脚のトラブルは生じます。そのため、外回りの手術室看護師は、脚のトラブルを回避するために、市販の弾性ストッキングを着用している方もいます。また、執刀する医師や直接介助の手術室看護師の邪魔にならないようにしながら、クッシングやストレッチをする方もいます。
直接介助の手術室看護師の立ちっぱなし
直接介助の手術室看護師は、静止している立ちっぱなしが多くあります。手術が始まると、直接介助の手術室看護師が動ける範囲は、極端に狭くなります。
活動範囲が狭い
直接介助の手術室看護師が術中に動ける範囲は、とても狭いです。消化器外科や婦人科、呼吸器などの術式では、足台の上り下りはほとんどありません。
足台は広いものと狭いものがあります。足台が広いものだと、足幅を広げて体幹が安定しますが、狭いものだと、脚を閉じた状態になりやすく体幹のバランスが崩れやすくなります。
直接介助の手術室看護師は、静止状態の立ちっぱなしが長くなりやすく脚のトラブルを生じやすくなります。そのため、脚のトラブルを回避するために、市販の弾性ストッキングを着用している方もいます。しかし、直接介助の手術室看護師は外回りの手術室看護師のように術中にストレッチをすることはできません。
直接介助の手術室看護師の中には、生じてしまった脚のトラブルに対しマッサージやツボ押しをしてケアをする方もいます。
腰痛
直接介助の手術室看護師の立ちっぱなしで生じるトラブルは脚だけではありません。
「腰痛」を訴える手術室看護師もいます。
直接介助の業務後に生じる「腰痛」は、手術室看護師の立ち方に問題があります。
通常、直接介助の手術室看護師の前には器械台があります。直接介助の手術室看護師は、器械台に体重をかける(前によりかかる)体勢になりやすいです。
長い時間、前のめりの体勢が続くことで腰痛が発症します。
手術室看護師の方の中には、腰痛の回避で「骨盤ベルト」や「腰痛ベルト」を使用している方もいます。また、手術が終わるとストレッチをする手術室看護師もいます。
脳貧血
直接介助の手術室看護師の立ちっぱなしで生じるトラブルに脳貧血もあります。
直接介助の業務は、「動く」範囲がとても狭い環境です。また、直接介助の業務では、脚を動かす頻度が極端に減ります。
脳外科手術や眼科の手術のようにマイクロを使用する術式では、直接介助の「動き」は極端に少なくなります。長い時間、動きの少ない立ちっぱなしを行うことで直接介助の手術室看護師は、脳貧血を起こしやすくなります。
静止した状態が長く続くようなときは、足首を動かす手術室看護師もいます。また、手術が長時間い及ぶときは、直接介助を他の手術室看護師と一時、業務を交代することもあります。
まとめ
手術室看護師の立ちっぱなしによるトラブルをご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。
「立ちっぱなし」は、下腿に血液が停滞することでうっ血を起こします。うっ血を起こすことで、むくみが出たりだるさを感じるようになります。
脚のトラブルを回避する方法に市販の弾性ストッキングの着用があります。その他にも脚のマッサージやツボ押しなども有効と言われています。
手術室看護師の業務は、「立ちっぱなし」な時間が多くあります。
外回りの手術室看護師は、立っている時間は長くありますが動く動作が多いため、直接介助の手術室看護師に比べて脚のトラブルが生じる頻度は少ないです。
外回りの手術室看護師は、市販の弾性ストッキングを着用したり、執刀する医師や直接介助の手術室看護師の邪魔にならないようにしながら、クッシングやストレッチことで脚のトラブルを回避する方もいます。
直接介助の手術室看護師が術中に動ける範囲は、とても狭く静止している状態が長いため脚のトラブルを生じやすくなります。
手術で用いる器械台は、直接介助の手術室看護師の前にあります。、器械台に体重をかける(前によりかかる)体勢になることで直接介助の業務後に「腰痛」が生じやすくなります。
脳外科手術や眼科の手術のようにマイクロを使用する術式では、静止した状態の立ちっぱなしが長くなりやすいです。静止した状態が長いと脳貧血を起こしやすくなります。
手術室看護師の方で立ちっぱなしの業務がつらく転職を考えているようでしたら、一度、転職サイトに相談をしてみてください。
ご紹介した立ちっぱなしのトラブルはごく一部です。仕事環境によって立ちっぱなしのトラブルは異なります。
転職サイトは、あなたの仕事環境が立ちっぱなしの業務によるトラブルをさらに助長していることを理解してくれます。是非、一度、相談をしてみてください。
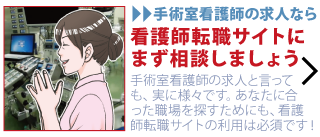
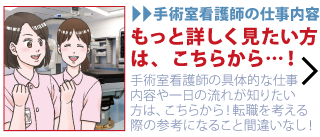
執筆者情報
 手術室看護師の求人と転職について、もっと詳しく!! 編集部
手術室看護師の求人と転職について、もっと詳しく!! 編集部
手術室看護師の求人と転職について、もっと詳しく!!は、厚生労働大臣から転職サポート(有料職業紹介事業)の許可を受けた(許可番号13-ユ-314851)株式会社ドリームウェイが運営するメディアです。転職サポートの経験を活かし、定期的なリライトや専門書を用いたファクトチェックなど、ユーザーに正確な最新情報を届けられるよう努めています。